検討会 関係事業者ヒアリング「ジャパン・リサイクル資料」より
「プラスチック製容器包装に係る燃料ガス化等(生成されたガス等をそのまま燃焼させているもの)に関する検討会」
傍聴できなかったので、環境省(中環審)の資料公開を待っていたが、、経済産業省(産構審)の審議会になるのだ~
容リ法の見直し論議は、環境省と経産省の審議会の合同会合だったけど、、、

プラスチック製容器包装に係る燃料ガス化等(生成されたガス等をそのまま燃焼させているもの)に関する検討会(第1回)‐配布資料 議事次第(PDF形式:115KB)
資料をみる限りでは、
プラスチックのケミカルリサイクルと位置づけている「ガス化手法」の見直し論議かな、、、
「生成されたガス等をそのまま燃焼させているもの」として
ジャパン・リサイクル、水島エコワークス、オリックス資源循環の3社からのヒヤリングということのようだ、
資料では、
ジャパン・リサイクルと水島エコワークスは同じ内容で、現状は「再商品化ガスは、製鉄会社が所内の発電所の燃料として利用」で、今後の考え方として「時代の要請を受けて、『水素社会』の一翼を担うべく水素ガスとしての利用を図る。(製鉄会社・化学会社に水素製造用の原料ガスとして販売する)」となっている。 オリックス資源循環の資料は現状のリサイクルフローがあるのみ、
やっと今頃という気もするが、、、
なにしろ、容リ法の指定法人ルートの入札制度、
市町村はリサイクル手法も選べない、再商品先も選べない、
プラスチックを焼却する自治体が増えてきているなか、
焼却よりも事業者負担の資源化を選んで、市町村は大変な経費と住民の手間をかけて分別収集をしている。
容リ法のプラスチックリサイクルが、自治体の焼却炉で燃やす廃棄物発電と同じではどうしようもない、
今後、どのような結論がでてくるのか?


(再掲)
■ プラスチック製容器包装に係る燃料ガス化等(生成されたガス等をそのまま燃焼させているもの)に関する検討会について2017年04月17日
現状の再商品化手法の見直し議論?
それとも何か新たに考えているということ?
現状のケミカルリサイクルとして認められている「ガス化」というのも、、
昭和電工はまだしも、、、
(昭和電工は水素と二酸化炭素の合成ガスを作りそれぞれアンモニア、液化炭酸ガスの原料に )
オリックス資源循環、ジャパン・リサイクル、 水島エコワークスの「ガス化」は、
産業廃棄物などと一緒にサーモセレクトガス化溶融炉で燃やしているのだから虚しい限り、
ジャパン・リサイクルの場合、回収ガスは製鉄所の燃料として利用、
ガス化という名の廃棄物発電もあるようだし、、
それ以前の問題として、
市町村できれいに分別して集めたプラスチック製容器包装を、産廃と一緒に燃やすのだから、
自治体の焼却炉で燃やしての廃棄物発電となにがちがうのか、、、、
プラスチック製容器包装の再商品化手法
現状で認められているのは ↓ ↓

リサイクル 油化※ 異物の除去、破砕、脱塩素、熱分解、精製その他の処理をし、炭化水素油を得る 高炉還元剤化※ 異物の除去、破砕、塩ビ除去、検査、分級その他の処理をし、高炉で用いる還元剤を得る コークス炉化学原料化※ 異物の除去、破砕、塩ビ除去、検査、分級その他の処理をし、コークス炉で用いる原料炭の代替物を得る ガス化※ 異物の除去、破砕、熱分解、改質、精製その他の処理をし、水素および一酸化炭素を主成分とするガスを得る 固形燃料等※ 塩ビ除去後、固形燃料等の燃料を得る
(固形燃料化は、緊急避難的・補完的手法として認められているが、これまでに入札参加はない)
●平成29年度 再商品化事業者落札数量 (プラスチック製容器包装)
平成29年度、全国的にみると、
やはり新日鐵住金のコークス炉化学原料化が一番多い
プラスチック製容器包装 合計(白色トレイ除く)
プラスチック 合計 664,821 トン
・コークス炉化学原料化 216,440 トン
・合成ガス化 76,563 トン
・高炉還元剤化 36,300 トン
・材料リサイクル 335,518 トン
落札単価(加重平均)(消費税抜き)
・コークス炉化学原料化 49,659円/トン
・合成ガス化 35,453円/トン
・高炉還元剤化 39,325円/トン
・材料リサイクル 54,897円/トン

関連(本ブログ) ジャパン・リサイクルの見学記 ↓ ↓
■ 容リプラ再商品化施設見学 ケミカルリサイクル(ガス化)/ジャパン・リサイクル 2009年05月23日

























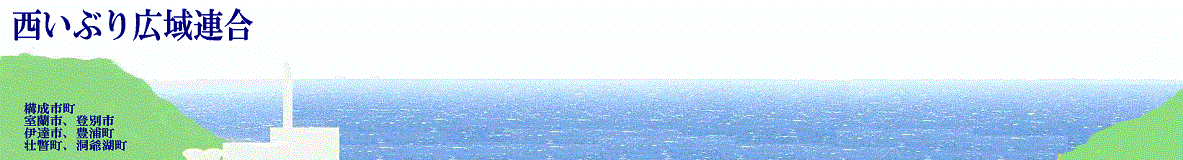






 白老町「
白老町「
 総人口
17,488人
男
8,352人
女
9,136人
世帯数
9,539世帯
基準月
平成29年3月末
総人口
17,488人
男
8,352人
女
9,136人
世帯数
9,539世帯
基準月
平成29年3月末