グラフは環境省「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成26年度実績)」より作成
環境省のホームページで、産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成26年度実績) が公表された。平成27年4月1日現在で、中間処理施設数は18,680施設、最終処分場は1,827施設とのこと。
また、12月に公表された、産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成26年度実績)からみても、産業廃棄物の量は、一般廃棄物に比べて膨大にあるということがわかる。参考(環境省 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成26年度実績)について<平成26年度総排出量約3億9,284万トン>)
一般廃棄物と産業廃棄物の比較
平成26年度総排出量
一般廃棄物 : 4,432 万トン(前年度 4,487 万トン )
産業廃棄物 : 約3億9,284万トン(前年度約3億8,464万トン) ← 一般廃棄物の約8.9倍
平成26年度焼却施設数
一般廃棄物焼却施設: 1,162施設
産業廃棄物焼却施設: 3,151施設
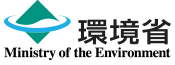 2017年4月21日
2017年4月21日
今般、平成26年度実績を取りまとめましたので公表いたします。 1.産業廃棄物処理施設の設置状況(平成27年4月1日現在) ・中間処理施設数 18,680件 (対前年 11件減) ・最終処分場数 1,827件 (対前年 53件減) 2.産業廃棄物処理業の許可の状況(平成27年4月1日現在) ・産業廃棄物処理業 198,648件 (対前年 3,227件減) ・特別管理産業廃棄物処理業 20,056件 (対前年 568件減) 3.行政処分等の状況(平成26年度実績) (1)立入検査等 ・報告徴収の件数 (法第18条) 4,684件 (対前年 440件減) ・立入検査の件数 (法第19条) 186,482件 (対前年 5,190件増) (2)行政処分 ・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数
(法第14条の3及び第14条の3の2) 330件 (対前年 83件減) ・特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数
(法第14条の6) 11件 (対前年 15件減) ・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数
(法15条の2の7及び法第15条の3) 41件 (対前年 22件減) ・改善命令の件数(法第19条の3) 43件 (対前年 2件増) ・措置命令の件数(法第19条の5及び第19条の6) 12件 (対前年 10件減) 4.広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収等に関する状況(平成27年度実績) ・広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収量 628,635t (対前年 61,591t減) ・再生利用認定業者による産業廃棄物の再生利用量 134,164t (対前年 4,847t増) 5.産業廃棄物の最終処分場の残存容量等について(平成27年4月1日現在) ・最終処分場の残存容量 16,604万m3 (対前年 576万m3減) ・最終処分場の残余年数 16.0年 (対前年 1.3年増) 添付資料 産業廃棄物行政組織等調査報告書(平成26年度実績) [PDF 2.3 MB] 産業廃棄物処理業の許可等に関する状況 [PDF 273 KB]
グラフで比較をしてみたものの、
施設の規模や稼働状況など関係なく,単に施設の設置数なのであまり意味はないのだが、、、
とりあえず、産業廃棄物の発生量が多いので、処理施設も多いということはよく分かる
産業廃棄物処理施設(中間処理施設数)、
全国18,680施設のうち、いちばん多いのは、木くず又はがれき類の破砕施設の 9,711施設(52%)
そのうち焼却施設は、
汚泥の焼却施設 618、廃油の焼却施設 613、廃プラスチック類の焼却施設 750、その他の焼却施設( 汚泥、廃油、廃プラスチック類、PCB を除く) 1,150施設
PCB廃棄物の焼却施設が20施設となった。(低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定)
●焼却施設のみ抜粋

産業廃棄物の最終処分場は1,827施設

●焼却施設の許可数は年々減少傾向ではあるが~
焼却総量や施設規模は??

●都道府県別でみると、中間処理施設数は北海道、静岡、愛知、福岡が多い、、
焼却施設だけをみると、北海道、千葉、神奈川、静岡、愛知、兵庫も設置数は多い

●都道府県別でみると、最終処分場は北海道、静岡が多い、、

参考
東京都環境局↓↓ 汚泥の焼却施設等除く、
■産業廃棄物の焼却施設一覧(平成21年4月1日更新) 16施設
23区内の産業廃棄物の焼却施設と処理能力 抜粋
(株)シンシア(品川区):130t/日
(株)櫻商会(大田区):5t/日
日本衛生(株)(足立区):7.7t/日
東京臨海リサイクルパワー(株)(江東区):550t/日、100t/日
前田道路(株)(江東区):95t/日
(株)協和メディカル(足立区):1.09t/日
関連(本ブログ)
■ 環境省 日本の廃棄物処理 平成27年度版(平成29年3月) 一般廃棄物の総排出量は4,398万トン ごみ直接焼却率は 80 %~ 2017年03月31日
■ 環境省 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成26年度実績)について<平成26年度総排出量約3億9,284万トン> 2016年12月22日」













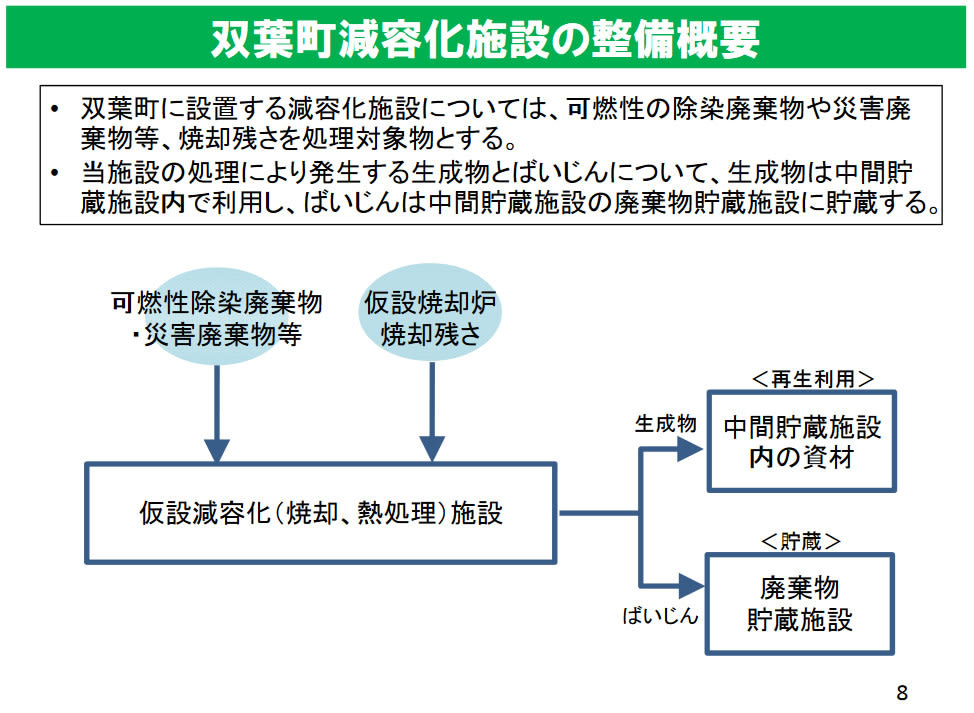
















 図2 産業廃棄物焼却発電実証プラントシステム概要図
2.今後の予定
図2 産業廃棄物焼却発電実証プラントシステム概要図
2.今後の予定