柳泉園組合有害ごみ保管場所
Business Journal「東京、ごみ焼却炉清掃工場が水銀排ガスを空気中に放出…周辺住宅地を汚染」より
青木泰氏の「水銀問題レポート」第二弾、
ごみ問題に関心を持つ人が少ない昨今、ある意味、こういうセンセーショナルなタイトルで危機感を煽っての問題提起もひとつの方策なのかもしれないが、なんだかな~ 内容的には、前回の「危険な水銀排ガス、これまで東京の空に放出が野放し…ごみ清掃工場の事故多発」とかわりばえしない。プラスチック焼却と関連づけもこじつけ、、というか、、
東京、ごみ焼却炉清掃工場が水銀排ガスを空気中に放出…周辺住宅地を汚染 Business Journal 2017年4月4日 文=青木泰/環境ジャーナリスト
都市部にあるごみの焼却炉を持つ清掃工場の周辺には、住宅地が広がる。その清掃工場のごみ焼却炉から水銀排ガスが放出されていれば、周辺住民の健康や環境の面で放置できない問題となる。
当サイトで以前、東京23区や三多摩地区でEUの規制値を超える水銀排ガスが、煙突から放出される事故が連続している事実を報告した。現在、環境省が国際水銀条約の発効に備えて進めている国内法の整備、改正大気汚染防止法では、現に起きている水銀事故に対して対応・対処できる内容になっているかが、まず問われることになる。
2010年に東京23区の5つの焼却炉で起きた水銀事故に際して、市民団体や専門家によりつくられた「水銀汚染検証市民委員会」の報告書「清掃工場の連続水銀事故の検証と課題」(環境総合研究所のHPより)では、プラスチック製品の焼却をやめることが主な対策になるとの提案がなされていた。
しかし「東京二十三区清掃一部事務組合」でごみを焼却する23区では、今も約半数がプラスチックを可燃ごみとする処理を改めていない。そのため事故が続き、ついに2016年4月までに18回の水銀事故が続いている。
13年に稼働した「ふじみ衛生組合」(三鷹市、調布市)でもすでに7回の水銀排ガスの放出事故があり、ここでもプラスチック製品を焼却していた。いずれの清掃工場でも自主規制値を設け、水銀自動測定器を設けていたために、事故をチェックすることができていた。
水銀の環境中への排出・放出から人の健康と環境を保護するために、環境省が設ける防止策にとって、現に事故を続ける事例の教訓化は大切である。環境省が今取り組もうとしている大気汚染防止法の改正が、そのような事情を考慮して進められているのかを検証したい。
意識的に有害物を燃やし、処分を受けた自治体 その検証に入る前に、プラスチック製品を焼却していないとする自治体での2つの水銀汚染事故事例も検証しておきたい。
東京都三多摩地区にある「多摩川衛生組合」(狛江市、稲城市、府中市、国立市のごみの焼却等を行う)の有害ごみの焼却事件(09年12月、10年2月)は、広く知られている。そして15年9月1日に起きた「柳泉園組合」(東久留米市、清瀬市、西東京市が構成市)での水銀事故の事例もある。
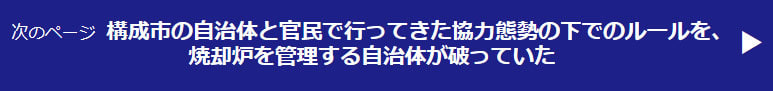

今回のレポート3ページ目で、
柳泉園組合の清掃工場で「13時間も水銀排ガスを高濃度に排出、放置」にからめて、
これに対して周辺市の市民が立ち上げた「柳泉園・ごみ焼却炉水銀汚染検証市民プロジェクト」の阿部聡子さん(西東京市)は、こう指摘した。
「血圧計などは焼却炉に投入され壊れてしまえば、水銀は一瞬のうちに蒸気になってしまう。事故によって放出された水銀が朝の9時から夜中の1時まで16時間も継続したことを考えると、業者が水銀血圧計を1~2台、間違って混入したという説明では辻褄が合わない。市民が疑問に感じたことに向き合わない行政を見たことが、プロジェクト立ち上げの理由である」
柳泉園組合では年間約100トンの水銀混入有害ごみが構内に集められ、有害ごみは誰でも入れるところに置かれたことがわかっている。よからぬ業者の不法投棄よりも、有害ごみの管理・保管が杜撰で、職員が深く関与していた事例であることをうかがわせた。
としているのだが、、、
2009年に、多摩川衛生組合で「有害ごみ(廃蛍光管)の不適正処理」という問題もあったのでそういう勘ぐりもしたくなるのだろうが、、、しかし、同じ多摩地域で、そういう大問題となったあとに、まさかそんなことありえないとおもうが、、、、、信頼関係がないということは、全てを疑ってかかるということなんだろうな、、、
関連(本ブログ) 最近の青木氏のBusiness Journal投稿記事
■ 危険な水銀排ガス、これまで東京の空に放出が野放し…ごみ清掃工場の事故多発 2017年02月01日
■ ルール破りの不燃プラスティック焼却 収集された不燃ごみ、大半が焼却処理…東京で蔓延、危険な有害化学物質を空気中排出 2017年01月07日
■ 東京3市(柳泉園組合)、ごみ焼却業務をゼネコンに丸投げの15年間包括契約…中止を求め住民監査請求 2016年12月01日
多摩川衛生組合の当時の有害ごみ焼却の報告書などを読み直してみようとおもったら、、リンクがなくなっていた。
・「調査報告書「有害ごみ焼却試験」 平成22 年11 月10 日 多摩川衛生組合事故等調査委員会
・「調査報告書「有害ごみ不適正処理」 平成22 年12 月10 日 多摩川衛生組合有害ごみ不適正処理調査委員会
2010年(平成22年)、多摩衛生組合では一時保管している廃蛍光管を、蛍光管破砕機の故障や保管用のドラム缶が不足したためとして、クリーンセンター多摩川の運転管理委託業者が廃蛍光管を焼却炉に投入した。
それに先立つ、2009年(平成21年)には、多摩衛生組合は、「有害ごみ焼却試験」として、廃乾電池3.31 トン、廃蛍光管3.43 トンの焼却試験を実施している。(有害物質の排ガス規制値の不存在を根拠に有害ごみの焼却試験を実施)
こういう過去の汚点は隠さず公表し続けるべきなのに、「有害ごみ焼却試験」も、「有害ごみ不適正処理」も報告書のリンクが切れて、替わりにというか、「事故等再発防止対策報告書 - 多摩川衛生組合」が更新されている~

 信頼回復へ
信頼回復へ
かつて多摩川衛生組合が起こした「有害ごみ焼却試験」や「有害ごみの不適正処理」のたび重なる不祥事で、日の出町当局をはじめ町議会、町民の皆様、そして二ッ塚廃棄物広域処分場を運営する東京たま広域資源循環組合および構成団体、搬入団体の方々に多大なご心配、ご迷惑をお掛けし、他方面にわたり信頼と信用の失墜を招いてしまいました。
また、平成22 年6月に発生した塩酸漏えい事故では、清掃工場の安全・安定運転や多摩地域のごみ処理広域支援体制に対し、大きな問題となってしまいました。
今後においては、一刻も早くこれらの不祥事の直接的原因に対する改善策を組み立て実施するとともに、その背景となる構造的原因に対する改善策として運営管理体制の強化や受託事業者への指示の徹底、情報公開等の充実、職員の意識改革と安全教育の徹底を図り、失った信頼を取り戻すよう全力を挙げて立て直しに取り組まなければなりません。
事故等再発防止推進委員会としましては、再発防止に当たり、事故等調査委員会から提言された再発防止策や東京都環境局、広域資源循環組合の指導・助言に基づき、的確な内容により着実な実施を行うための検討を行い、以下のとおり報告書としてまとめました。
今後、この再発防止策の進行管理を行うとともに、事務改善のための業務の点検や見直しも検討していくこととしました。
詳細につきましてはダウンロードより「事故等再発防止対策報告書」をご閲覧下さい。
 事故等再発防止対策報告書(1183KB)(PDF文書)
事故等再発防止対策報告書(1183KB)(PDF文書)
参考、東京たま広域資源循環組合HPでは
多摩川衛生組合関連 多摩川衛生組合の不適正処理に関する対応の経緯について 多摩川衛生組合における廃蛍光管の不適正処理について 多摩川衛生組合における有害ごみ(廃乾電池・廃蛍光管)焼却試験について 多摩川衛生組合の不適正処理に関する対応の経緯について多摩川衛生組合の廃棄物処理について、平成22年度に、有害ごみの試験焼却及び廃蛍光管の不適正処理を行っていたことが発覚し、多摩川衛生組合からの焼却灰について、循環組合では、一時搬入停止の措置を行いました。
循環組合では、こうした事態を重くみて、多摩川衛生組合のみならず、全ての組織団体及び搬入団体において、適正なごみ処理が行われるよう再発防止策をとりまとめ、着実に実施してまいりました。
平成23年1月から4月にかけて、搬入団体の全ての清掃工場に立入調査を実施したところ、清掃工場の運転管理の状況等について、問題となりうる事項は見受けられませんでした。また、多摩川衛生組合には、5回立入調査を実施し、多摩川衛生組合が策定した再発防止策が着実に実施されていることを確認しました。平成24年度には、全搬入団体の清掃工場のほか、中間処理施設についても立入調査を行いましたが、問題となりうる事項は見受けられませんでした。
また、組織団体及び搬入団体の職員等が、適正な廃棄物処理が不可欠であることを改めて認識することを目的として、平成23年度は7回、平成24年度は6回、処分場での見学会を実施しております。平成25年度もすでに3回見学会を実施しており、合計6回の開催を予定しております。実施内容は、現場視察に加え、処分場設置の経緯や公害防止協定等の内容について理解を深めるものとしております。
なお、多摩川衛生組合では、事故等再発防止対策として、61項目の対策を実施するとしておりましたが、平成25年3月までに全ての項目について対策を完了したとの報告を受けております。
循環組合では、引き続き搬入される廃棄物の適正化に向けた取り組みを進めてまいります。
平成25年9月5日
ページトップへ 多摩川衛生組合における廃蛍光管の不適正処理についてこの度、多摩川衛生組合が、昨年度(平成21年度)有害ごみの焼却試験を行ったにもかかわらず、廃蛍光管の不適正処理を行っていたことが判明しました。
有害ごみの分別処理・処分の原則に反し、廃蛍光管の焼却灰の搬入を防ぐことができなかったことについて、循環組合の管理者として責任を痛切に感じております。今回の件の背景には、多摩地域の自治体にごみ処理に対する危機感の欠如があるのではないかと推察しており、「三多摩は一つなり」の精神に基づき最終処分場を受け入れていただいている日の出町の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。
循環組合は、今回の多摩川衛生組合の不適正処理に対し、平成22年11月9日から多摩川衛生組合の焼却灰の受入れを停止しました。その後、多摩川衛生組合が示した再発防止策の方向性が妥当であると判断し、日の出町の皆様にも御了承が得られたため、平成22年12月8日から焼却灰の受け入れを再開しました。
廃蛍光管の不適正処理が行われたと推定される時期及びそれ以降において、日の出町及び地元自治会等と締結している公害防止協定に基づく下水道への放流水及び排ガスの測定値は、基準に適合しておりました。このことから、多摩川衛生組合からの焼却灰が循環組合のエコセメント化施設に搬入されことに起因する周辺環境への影響はなかったことを確認しております。
しかしながら、今回の不適正処理は、職員が通常業務の中で意識的に行った点で、昨年度(平成21年度)の有害ごみ焼却試験よりも重大な問題を含んでおります。このため、多摩川衛生組合についてはもちろん、全ての組織団体及び搬入団体において適正なごみ処理が行われるよう、再発防止策をより強化しました。
今回の件を教訓として、私は、今後、水銀やPCBを含む有害ごみについて、分別処理を着実に実施することによって焼却処理を行わないことをお誓いいたします。また、多摩地域400万人の暮らしを支えるため、私が先頭に立ち、役員及び職員一丸となって、失われた日の出町の皆様の信頼を回復し、皆様に安心していただけるように誠心誠意対応してまいります。
平成22年12月28日
東京たま広域資源循環組合
管理者 黒須 隆一
この度、多摩川衛生組合が、廃乾電池と廃蛍光管合計8トンの焼却試験を行い、この焼却灰が東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬入されていたことが判明しました。
循環組合では、日の出町及び地元自治会等と締結している公害防止協定の前提である有害ごみの分別処理の原則に反して、本来、日の出町に搬入されるべきではない焼却灰の搬入を防ぐことができなかったことについて責任を痛感しており、日の出町及び関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。
循環組合のエコセメント化施設は、焼却灰に含まれる重金属類を回収できる能力を有しています。また、今回の焼却試験の焼却灰に含まれる重金属類は法に定められた基準値以下であり、さらに、この焼却試験で発生した焼却灰が搬入された以降も、公害防止協定に基づく下水道への放流水及び排ガスの測定値は基準値を満たしておりました。このことから、焼却試験の焼却灰がエコセメント化施設へ搬入されたことに起因する周辺環境への影響はなかったことを確認しております。
これまで培ってきた日の出町及び関係者の皆様との信頼関係を損ない、今回の焼却試験の焼却灰の搬入を防ぐことができなかった事案の重大性に鑑み、責任の所在を明確化するため、循環組合の管理者は、その職を辞することとしました。
また、今後の再発防止策として循環組合では、今後の多摩川衛生組合や各組織団体への有害ごみの処理に関する監視強化を行うとともに、搬入不適廃棄物の搬入防止に向けた規定整備を行ってまいります。さらに、これまでの歴史を風化させず、公害防止協定等を遵守するための啓発活動の充実を図ります。
循環組合におきましては、新管理者を筆頭に役員及び職員一丸となって、再発防止策の徹底を図るとともに事業を着実に運営することにより、失われた信頼の回復に努めてまいります。
平成22年11月2日
多摩川衛生組合における有害ごみ(廃乾電池・廃蛍光管)焼却試験に関する報告書【PDF:1.93MB】
